■第ニ章 実験方法
ガラスの小球を作成する。普通のガスバーナーで細工するので、軟質のガラスを利用する。図1のように毛細管を作り、その先を加熱してガラス球を作成する。ガラスの小球は直径0.5〜1cm程度が良い。
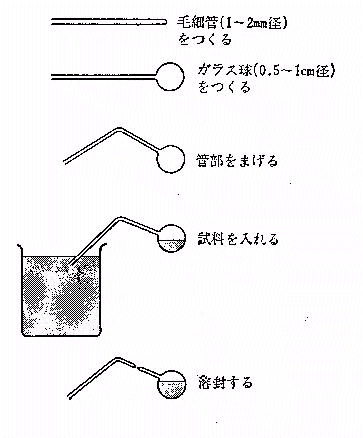
図1 ガラスの小球の作成と液体試料の取り込み
(文献より引用)
アセトンの取り込みは、ガラス小球を少し温めて、毛細管の先に液体を差すと冷えて吸い込まれる。吸い込まれたら先を溶封する。このように液体試料を5つ程度作成する。
次に、図2のようなビクトル・マイヤー装置を設置する。水溜め(水準瓶)を上下させて加熱管内が密閉状態になっているかを確認する。ガラスの接続部分がゴム管で繋がれているので、古いゴム管は空気漏れが生ずるので交換した方が良い。
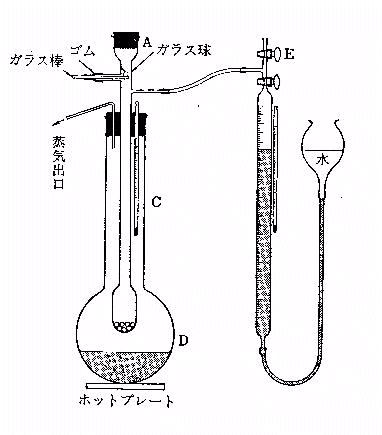
図2 ビクトル・マイヤー装置
(文献より引用)
まず、ヒーターで装置のフラスコD部分の水を沸騰させておく。先に作成したガラス小球の試料を装置Aのガラス棒上にセットする。そのとき、落ちたときに割れやすくするためにガラス球の毛細管部分にガラスの重りをつけるとよい。
ガラス球を落下させると、底に当たって破壊されて一気に蒸気化してガスビューレットの空気を押し下げるので、それに合わせて水溜め(水準瓶)下げてやる。押し下げられたビューレットの水位の目盛を読む。
以上の操作を5回程度繰り返して、アセトンの分子量を求める。